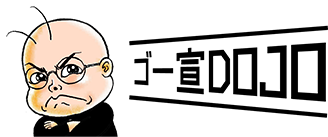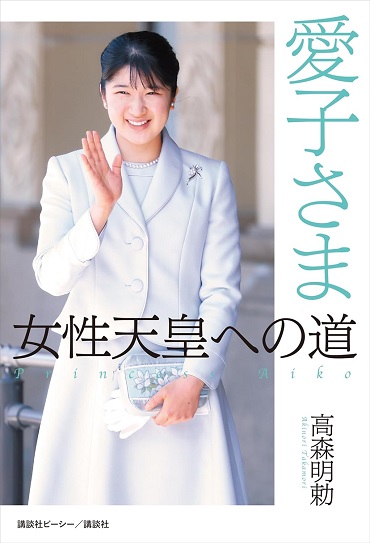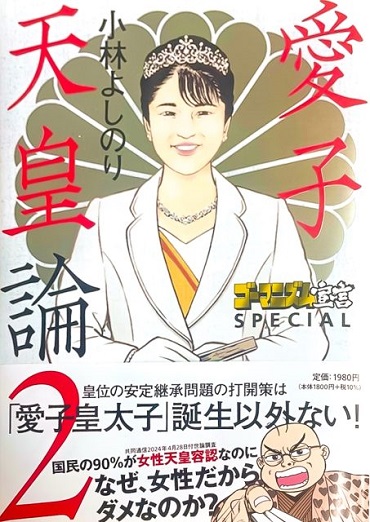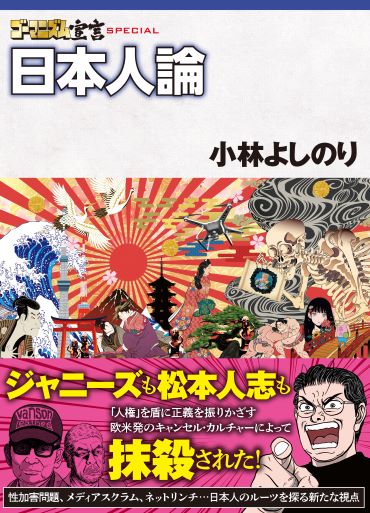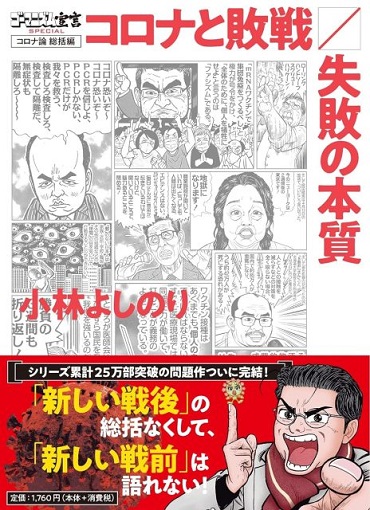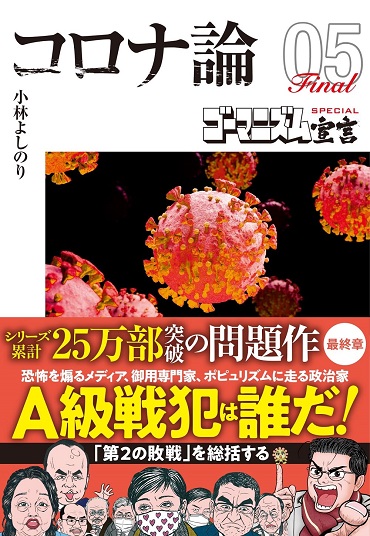先週の頭から数日間、
「平城遷都1300年祭」で盛り上がる
奈良へ取材に行ってきました![]()
日頃は起きてから寝る直前まで、
椅子に座ってひたすら仕事をしている
よしりん先生の足は
筋力が落ち、退化し始めています。
その上、暑さにとことん弱い。
奈良は盆地ですから、
東京よりもさらに厳しい暑さが
予想されます。
さらに、奈良と言えば、
8年前、よしりん先生が
ヘルニアの腰痛を発症した
曰く付きの地でもあります。
あな、恐ろしや・・・

( ↑ 『新ゴーマニズム宣言15巻』収録。
最後に示した決意は、一体どこへ行ってしまったのでしょう?)
無事に取材を完遂できるのか、
いくつもの不安要素を抱え
出発したのでした![]()
奈良駅に着いた途端、至る所に、
例のマスコットキャラクター
“ せんとくん ” が出迎えてくれます。


この“ せんとくん ”
絵で見ている分には「キモカワイイ」
と思えなくもないのですが、
ぬいぐるみとなると、
色合いや質感の問題からか、
「鹿の角が生えた仏像」
という不気味さを再認識させられます
でも彼も、この猛暑の中、
頑張っているのですよね。
奈良の取材では、
よしりん先生がブログに書いたように、
古代の天皇や皇后に関係する陵墓やお寺、
そして平城遷都1300年の今年、
完成したばかりの
「平城宮跡会場」などを取材しました![]()
![]() 取材した、ほんの一部をご紹介
取材した、ほんの一部をご紹介 ![]()

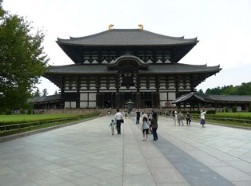
↑ あまりの暑さに、鹿もバテ気味・・・ ↑ 聖武天皇の詔によって建立された「東大寺」
↑ 聖武天皇の詔によって建立された「東大寺」


↑ 必死になって大仏様の指の形を真似する ↑ 古代の天皇のお墓。さて、どの方でしょうか?
よしりん先生・・・


↑ 「平城宮跡会場」に復元された「朱雀門」 ↑ 「朱雀門」から望む「大極殿」。遠っ![]()

「平城宮跡会場」の目玉である
「大極殿」がどんな物だったかは、
よしりん先生が作品に描くのを
楽しみにお待ち下さい![]()
しかし、この「平城宮跡会場」、
とんでもない広さで、
しかも日差しを遮るものが、
ほとんどないのです
そんな中をひたすら歩いて移動・・・![]()
最初、熱中症になったら大変だと、
私が持って行った日傘を
先生に貸そうと思ったのです。
最近は「日傘男子」なる者もいるようですし
しかし、やっぱり日傘は
殿方には似合わないものでした・・・![]()

私が奈良へ初めて行ったのは、
中学校の修学旅行でした![]()
今思うと、あの時は、
奈良に都があったことの意味や歴史など、
全くわかっていなくて、
ただただ、同級生との初めての旅行に
はしゃいでいただけでした
ま、中学生なんてそんなものかな
でも、「修学旅行」なんだから、
学校でもう少しわかりやすく、
教えておいてくれても良かったのに・・・。
さて、奈良取材のあとは、
伊勢へ移動です![]()
![]() 「そうだ、伊勢へ行こう
「そうだ、伊勢へ行こう![]() 」
」 ![]()
東京に帰る前に、
奈良から近鉄特急に乗って、
伊勢へ行ったわけは、
私の「TEL友」(笑)
田中卓大先生を訪ねるためです![]()

古代のこと、天皇のこと、
皇統問題について等々、
様々なことを教えて頂きました![]()
![]()

そしてもちろん、伊勢に来たからには、
伊勢神宮 を参拝しないわけにはいきません![]()
高森先生に叱られたからか、
鳥居をくぐる時から、
しきりに作法を気にして歩くよしりん先生・・・


伊勢神宮は、3年後の平成25年に、
20年に一度の “ 式年遷宮 ” が予定されています。
鳥居をくぐって直ぐに渡る「宇治橋」は、
その式年遷宮に向けて架け替え工事が進められ、
昨年、完成したばかりです。
とても綺麗で、
時々、檜の香りがふわっと漂います![]()


↑早足で木陰に逃げるよしりん先生・・・![]()



↑ 五十鈴川にて。 ↑ 午前中の早い時間帯だったので、 ↑ 最も神聖な場所なので
まさか、この時、あんなことを 普段以上に静謐な雰囲気 写真はここまで
考えていたとは・・・
夏休みだからなのか、
家族連れや恋人同士など、
参拝者がとても多くて驚きました
小さい男の子の手をひいて宇治橋を渡りながら、
「行く時は右側を歩いて、帰りは反対側を歩くんだよ」
と教えている若いお母さん。
正宮までの長い参道に疲れ
ぐずりだしてしまった子を
なんとか宥めながら連れて行く若いお父さん。
見ていて、とても微笑ましかったです
何か特別な信仰心を持ったり、
愛国心を居丈高に叫んだり、
そんなことをしなくても、
親から子供へ伝わっていく
「皇祖神」への自然な信仰のあり方は、
今も昔と変わらずに
まだまだ残っていることを感じました![]()

さて、参拝の後は必ず、
おはらい町「おかげ横丁」に
寄らなければいけません![]()

ここは歩いているだけでも
楽しい気持ちになりますよ![]()
お店から漂ってくる美味しそうな匂いに
「全部、食べたい![]()
![]() 」
」
と誘惑されちゃいます![]()


↑色々あったけど、「赤福」はやっぱり美味しかった![]()
さて、長々と書きましたが、
猛暑の中、なんとか無事に
奈良・伊勢取材を終えることができました
![]()
ここには書けなかった
爆笑エピソードがたんまりとありますので、
作品化を楽しみにお待ち下さい![]()